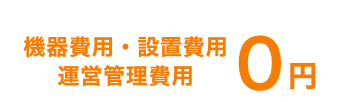固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの固定資産に対して課される税金です。毎年1月1日時点で不動産を所有している人が課税対象になり、所有する不動産の評価額にもとづいて税額が算出されます。
この記事では、土地にかかる固定資産税についての考え方や、税負担を抑える方法などを解説します。土地を所有しており、特に使用していない土地について固定資産税を抑えたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

土地にかかる固定資産税の計算方法
土地にかかる固定資産税を計算するには、固定資産税評価額と課税標準額を知ることが必要です。それぞれについて詳しく説明するとともに、計算式も併せてご紹介します。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額(課税標準額)に、各自治体が定めた税率をかけることで算出できます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
固定資産税評価額は、固定資産評価基準により、土地や建物などの固定資産の価値をもとに市町村(東京都23区内の場合は都)が評価し、決定した額のことです。評価額の算出は、土地の現況や用途、地目に応じて行われます。
課税標準額は、固定資産税を計算するための基準となる金額のことです。課税標準額は、通常、固定資産税評価額となりますが、土地においては、住宅用地に対する特例措置や税負担の調整措置が適用されることによって、課税標準額が固定資産税評価額よりも低くなることがあります。標準税率については、各自治体が自由に定められますが、多くの場合、標準税率である1.4%が採用されています。

固定資産税の評価替えとは?
固定資産税の納税額は、毎年同じとは限りません。なぜなら「評価替え」という制度により、固定資産税の評価額は、3年の周期で全国的に見直されるためです。評価替えの年度を基準年度といい、次回は2027年度になります。もし地価が下がった場合は、税額が低く見直される可能性もありますので、確認しておきましょう。
都市計画税とは?
土地によっては、固定資産税のほかに都市計画税がかかる場合もあります。原則として都市計画税は、都市計画法によって指定された市街化区域内に、土地や建物を所有している人に対して毎年課税される税金です。固定資産税と同じく、固定資産税評価額(課税標準額)に税率をかけて算出します。都市計画税の税率は各市町村(東京都23区内の場合は都)によって設定されており、上限は0.3%と制限されています。都市計画税の計算式は以下の通りです。
都市計画税=課税標準額(固定資産税評価額)×制限税率(最高限度0.3%)

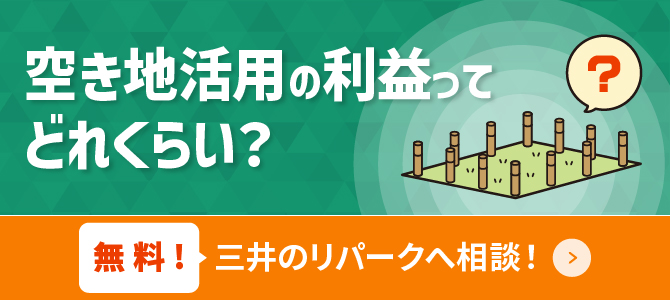
所有している土地の固定資産税の調べ方
所有している土地の固定資産税を調べるには、書類で確認する方法と土地の種類で確認する方法があります。それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
書類で確認する場合
固定資産税評価額を調べるのに役立つ書類は以下の通りです。
・公課証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
・固定資産評価証明書
・固定資産税の課税明細書
公課証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)は固定資産の所有者や評価額、課税標準額、税額などの固定資産課税台帳の記載事項を証明する書類です。取得を希望する人は、市町村の担当窓口(市民税課など)に申請して取得できます。
固定資産評価証明書は、固定資産税の課税対象となる資産の評価額を証明する書類のことです。公課証明書と同様に、市町村の担当窓口(市民税課など)に申請して取得できます。
固定資産税の課税明細書は、固定資産税と都市計画税が課税されている土地や家屋の所在・地番や価格などの状況を知らせている書類で、納税通知書とともに送付されます。
土地の固定資産税評価額を概算で知りたい場合、一般的に公示価格などの70%程度が目安とされています。おおよそでよいのでいくらかを知りたいという方は参考にしてください。

土地の種類で確認する場合
固定資産税の調べ方には、土地の種類に応じて課税標準額を確認する方法もあります。土地のみを所有している場合と、家屋が建っている土地では、課税標準額が異なるため注意が必要です。さらに、課税標準額には免税点と呼ばれる基準が設定されています。特に土地の場合、免税点は30万円です。課税標準額が30万円未満の場合は固定資産税の対象外になり課税されないので、この点を押さえておきましょう。
土地のみを所有している場合
土地に家屋が建設されていない場合、農地以外の建物が建っていない土地の課税標準額は「固定資産税評価額×0.7」です。ただし、正確な額は所有地を管轄する市町村の窓口に確認しましょう。
家屋が建っている土地を所有している場合
土地に家屋が建設されている場合、特定の条件にもとづいて固定資産税評価額が軽減される制度があります。評価額が減少すると課税対象が縮小され、結果的に固定資産税額も少なくなります。なお、居住している家だけでなく、空き家の場合でも固定資産税はかかりますので、注意が必要です。

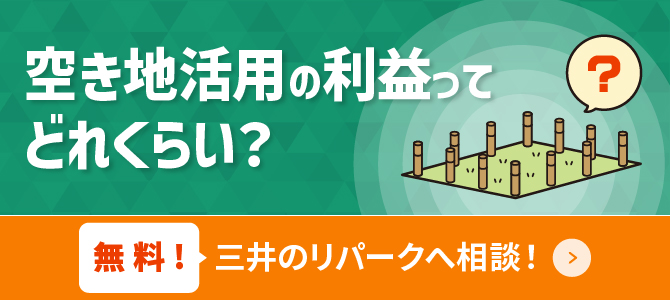
土地にかかる固定資産税の負担を抑える方法
ここからは、土地にかかる固定資産税の負担を抑えられる主な方法を3つご紹介します。
・住宅用地の特例を活用する
・書類と実際の土地に間違いがないか確認する
・土地を分筆する
住宅用地の特例を活用する
住宅用地の特例とは、マイホームやアパート、マンションなど人が居住するための建物が建っている土地の固定資産税が大きく減額されるというものです。この特例は、固定資産税を節税できる最も一般的な方法です。具体的には、以下のような軽減措置が適用されます。
| 住宅用地の区分 |
固定資産税 |
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) |
課税標準額が評価額の6分の1に減額 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) |
課税標準額が評価額の3分の1に減額 |
たとえば、評価額が3,000万円で200m2の土地の場合を考えてみましょう。この場合、特例適用前は、3,000万円×1.4%=42万円が固定資産税になりますが、特例適用後は、3,000万円×1/6×1.4%=7万円になり、かなりの節税が可能です。
この特例は、アパートやマンションなどの共同住宅にも適用されます。ただし、店舗や事務所との併用住宅の場合、居住部分の床面積が建物全体の4分の1以上であることが条件になるので注意しましょう。
書類と実際の土地に間違いがないか確認する
役所から送付される納税通知書や登記簿などを照らし合わせ、記載内容に誤りがないか確認することで、固定資産税を抑えられるケースもあります。特に、小規模住宅用地の特例が適用され、減額されているかは十分に注意して確認しておきましょう。
土地を分筆する
土地を分筆することで、固定資産税評価額を下げられる可能性があります。土地の分筆とは、登記簿に登録する際に、土地を複数に分割して登記することです。
分筆により、それぞれの土地の評価額が下がる場合があります。さらに、分筆することで、小規模住宅用地の特例(200m2以下)を最大限に活用できる点もメリットです。
ただし、分筆には測量費用などが発生するため、専門家に相談しながら進めましょう。

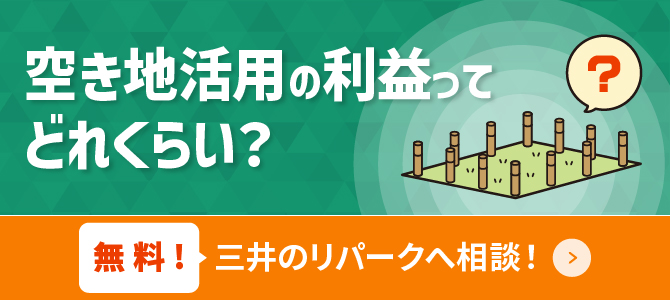
土地の固定資産税における節税方法と注意点
土地にかかる固定資産税の節税方法のなかには、多額の初期費用や多くの手間がかかったり、リスクが高かったりする方法もあることに注意が必要です。たとえば、住宅用地の特例を活用すれば高い節税効果が期待できるでしょう。しかし、住宅の新築は初期費用の負担が大きい側面もあります。さらに、賃貸住宅の経営にはコストがかかり、必ず入居者を集められるとは限りません。そのため、このような方法は、立地や土地(物件)の条件によって、投資リスクの高い方法といえます。
そこで選択肢の1つとして挙げられるのが、コストや手間を軽減しやすい土地活用で収益を上げ、その分を固定資産の納税に充てるという方法です。なかでも駐車場経営は、経営方法によっては安定した収入が得やすいというメリットがあります。また、一括借り上げ方式であれば、看板や料金精算機を設置する費用や運営管理費がかからない場合が多いでしょう。さらに、転用性も高いため、別の土地活用へ変更したり、土地そのものを売却したりする場合も短期間での切り替えが可能です。投資リスクも低いため、土地活用におけるおすすめの方法といえるでしょう。駐車場経営について、次でより詳しく説明します。

土地活用は駐車場経営がおすすめ
固定資産税の負担を抑えるために土地活用を行うなら、一括借り上げ方式での駐車場経営がおすすめです。一括借り上げ方式のメリットは主に以下の5つが挙げられます。
・安定した収入が得られる
・管理業務の負担が軽減される
・初期投資を抑えられる
・短期間での土地活用ができる
・管理会社の情報網とノウハウを活用できる
一括借り上げ方式の駐車場経営は、稼働率に関係なく一定の賃料が支払われ、集金、定期巡回、保守管理、機器点検、清掃、クレーム対応などを任せられることが一般的です。また、短期間での土地活用が可能であることから、将来の土地利用計画に柔軟に対応できるというメリットがあります。

駐車場経営なら三井のリパーク
土地の固定資産税を節税する方法はありますが、なかには初期費用が発生したり、リスクを伴うものもあったりするので注意が必要です。そのため、もし使用していない土地の固定資産税について不満を抱いている場合は、節税を考えるのではなく、その土地を上手に活用して収益を得て税負担を軽減させるという考え方もあります。
土地活用でいえば、特に一括借り上げ方式の駐車場経営がおすすめです。この場合、土地の所有者は駐車場運営会社に土地を貸し出すだけで、事業運営に必要な設備の導入から手間のかかる管理までを任せられます。プロの力を借りて、毎月一定の賃料を受け取れるでしょう。
なお、三井のリパークの一括借り上げ方式による駐車場経営であれば、駐車場経営に必要な設備費や設置費、運営管理費を負担することなく始めることが可能です。(※1)三井不動産グループの総合力を生かして、駐車場経営後に土地の売却を検討されている方の場合も最後までサポートします。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。